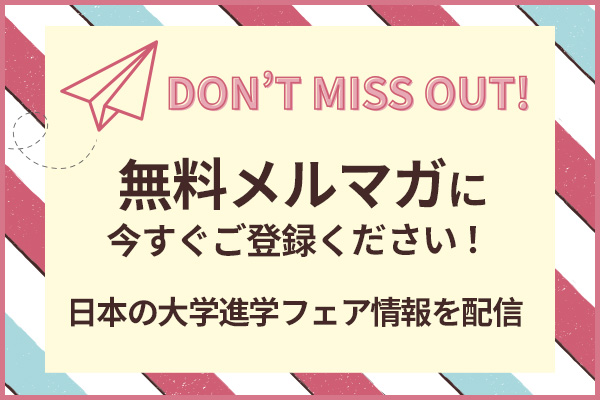近年、日本の大学はグローバル化に対応し、外国人学生や帰国生の受け入れを積極的に進めています。円安の影響もあり、アメリカの大学と比べて学費が抑えられる点も魅力の一つ。本特集では、アメリカ在住で日本の大学進学・留学を考える方に向け、役立つ情報をお届けします。巻末では、海外からの学生受け入れに積極的な国公立・私立大学も紹介。日本での学びを視野に入れる第一歩として、ぜひご活用ください。
◎海外からの日本の大学進学に関するイベント情報 »
日本の大学に行くメリットとは?
「日本の大学進学フェア」を開催しているライトハウス社でコーディーネーターを務める廣田恵子に、日本の大学に行くメリットについて聞きました。
近年、日本の大学は、国際化の推進を目指し、国公立・私立を問わず、積極的に海外からの学生を受け入れようとしているため、海外生が日本の大学に進学するメリットは大きいと言えます。
まず、英語圏から優秀な学生に来てほしいという思いもあり、アメリカの受験制度のように書類審査での合否決定、英語で学べるコース(学部)、秋入学、海外生のための奨学金制度などを整える大学も増えました。また、学業だけでなく、生活・メンタル面でのサポートを提供するなど、日本語能力や日本での暮らしに不安がある留学生を手厚く支援しています。
保護者にとっては負担の大きい学費も、文科省によると令和5年度の国公立大学における授業料は年間約55万円、私立大学(四年制)は平均すると約100万円からです。特に、アメリカに住んでいる人にとっては円安も追い風となっているでしょう。
アメリカ生まれや海外生活が長いお子さんにとっても、旅行や帰省などの一時的なものではなく、日本で地に足を付けて学業に励むことは人生においてとても良い経験になると思います。
気になる大学のキャンパスを見学する機会を設けたり、大学フェアなどのイベントに参加したりすると、お子さんはもちろん、保護者も進学・留学のイメージをしやすくなってくると思います。
参加校: 青山学院大学、開志創造大学 ※仮称(オンライン)、国際基督教大学(ICU)、駒澤大学、中京大学、同志社大学 ILA、山梨学院大学 iCLA、横浜国立大学、立命館大学
海外から日本の大学への進学・留学に興味を持ったら 〜 知っておきたいこと、やっておきたいこと
日本の大学は通常4月に新学期が始まりますが、近年では秋入学を導入している大学も増えています。出願期間は大学やプログラムによって異なりますが、一般的に入学前年の秋から冬にかけて行われます。各大学の公式ウェブサイトで最新のスケジュールを確認し、余裕を持って準備を進めましょう。
日本の大学に入学するまでのタイムライン&TO DOリスト
| 時期 | やること |
|---|---|
| 入学1年前 | □ 志望動機を明確にする □ 情報収集 進学・留学の理由や志望動機を明確にして、希望する大学に資料請求するなど大学の情報収集を行います。志望校の学校案内や入学願書を取り寄せ、出願資格を確認しましょう。 |
| 入学10カ月前まで | □ 志望校決定 |
| 入学9カ月前 | □ 受験資格を確認・取得 日本留学試験(EJU)に申し込みを行う(参考:2025年の出願受付期間は2/10〜3/6)。日本語能力試験(JLPT)、 TOEFL®、IELTS、TOEIC®などを必要に応じて受験する。 |
| 入学6カ月~8カ月前 | □ 出願 アドミッション提出、または入学願書や必要書類を志望校に送る。 |
| 入学2カ月~5カ月前 | □ 受験 書類選考、日本留学試験(EJU)、志望校の入学試験受験などを受ける。 |
| 入学3カ月前 | □ 入学準備 □ 入国手続き 志望校に合格し入学許可書を受け取ったら、入学金などを送金する。寮の手続きなど、日本で住む場所を決める。また、在留資格認定証明書(COE)を大学から受け取り、領事館で査証(ビザ)を申請する。 |
| 入学1カ月前 | □ 渡航手続き 航空券、保険を手配する。必要に応じて、寮や住居への入居準備を進める。 |
大学の情報収集
帰国生や外国人学生が日本の大学進学を考えた際に、最初に気になることから卒業後の進路まで、総合的にまとめたサイトがあるので、まずは以下を参考にしてみるといいでしょう。
- Study in Japan | ウェブサイト
政府公認の日本留学情報サイト。文部科学省、および外務省協力の下、日本学生支援機構が運営しています。 - 独立行政法人 日本学生支援機構 | ウェブサイト
奨学金、留学生支援、学生生活全般のサポートを行う日本学生支援機構の公式サイト。 - Japan Study Support | ウェブサイト
公益財団法人アジア学生文化協会による留学生情報総合サイト。英語で情報収集したい人向け。
※上記タイムラインは日本留学情報サイト「Study in Japan 日本への留学計画( https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/flow-chart/schedule.html )」から引用。
アドミッション 〜 留学生、帰国生向けの日本の大学の入試方法
アメリカなど海外に住む人が日本の大学に進学・留学する場合は、まず興味のある大学の入試方法を調べてみましょう。日本の大学の入試方法は多様化しており、一般選抜、AO入試(総合型選抜)、帰国生枠入試、留学生枠入試などがあります。帰国生や留学生向けの入試では、書類審査や面接が中心で、SATやACT、TOEFLなどのスコアが求められることが多いです。また、英語で学位を取得できるプログラムも増えており、英語のみで受験・履修が可能な場合もあります。各大学の入試要項を確認し、自分に適した入試方法を選択してください。当サイトの大学紹介ページに掲載の受験制度情報も参考にしてください。
日本留学試験(EJU: Examination for Japanese University Admission for International Students)
日本の大学(学部)に進学を希望する外国人留学生を対象にした試験。日本語の能力や、大学の授業についていくために必要な基礎学力を測るために実施されます。国際基督教大学(ICU)、上智大学、立命館アジア太平洋大学(APU)など、帰国生入試や英語プログラムではEJU受験を求めないとする大学もあります。志望大学の入試要件を確認し、必要なら受験準備を進めましょう。
概要や詳細は実施機関の日本学生支援機構(JASSO)のページ(英語)で確認を。
日本語能力試験(JLPT: Japanese-Language Proficiency Test)
日本語を母国語としない人を対象とした世界最大規模の日本語試験。レベルは5段階あり、日本の大学へ留学条件としては最も高い「レベルN1」か「N2」を求められることが多いようです。詳細についてはwww.jlpt.jpに記載。
重国籍者の入試規定を確認
日本と外国の重国籍を持つ学生の場合、受験資格や入試区分が大学によって異なる場合があります。「重国籍の中に日本国籍が含まれる場合は、日本人出願者とみなす」とする大学もあれば、「重国籍者は外国人留学生入試は出願不可だが、帰国生徒特別入試には出願可能」と定めている大学もあります。各大学の募集要項を確認し、自分の国籍状況に応じた適切な入試区分で出願してください。また国籍の選択によって、カリキュラム、留学生を対象とする奨学金の受給、学費などが変わってくることもあるため、事前に確認しておきましょう。
国籍を選択すべき期限
【2022年4月以前】
・ 20歳に達する以前に重国籍となった場合:22歳に達するまで
・ 20歳に達した後に重国籍となった場合:重国籍となった時から2年以内
【現在】
・ 18歳に達する以前に重国籍となった場合: 20歳に達するまで
・ 18歳に達した後に重国籍となった場合:重国籍となった時から2年以内
住環境を知る
留学生向けに学生寮を提供している大学も多く、入学初年度は寮への入居が必須とされる場合もあります。寮以外にも、アパートやシェアハウスなどの選択肢がありますが、大学のサポート体制や周辺環境を事前に考慮して志望校を選ぶと賢明です。住環境を知る方法として、大学が開催している「オープンキャンパス」「体験授業」「キャンパス見学」に参加すると、大学の担当者に直接確認することができるので、寮がある場合は見学させてもらえるかもしれません。また、大学周辺のアパートや町の雰囲気なども知ることができます。
日本の大学の学費はどれくらい?

日本の大学では、学費と呼ばれるのは一般的に「入学金(1年次のみ納める)」「授業料」のほか、「施設費」「実習費」「諸会費」などを合わせたものです。理系学部や医学・医療系学部では、特に学年が上がると実習費が多くかかる場合もあるので、卒業までにどれぐらいの費用がかかるか、トータルで見ることが大切です。
日本では大きく分けて「国立」「公立」「私立」に分かれており、ほとんどの国立大学が同じ金額を採用、公立大学は、都道府県や市など居住地によって入学金が異なるケースがあります(授業料は国立大学の金額にほぼ準ずる)。そして私立大学は学部・学科の種類などによって学費が異なります。
国公立大学の年間の授業料は約55万円。私立大学では年間約80万円〜320万円と学部や専攻によって幅があります。アメリカの大学と比較すると日本の大学の学費は比較的安価と言えますが、為替レートや生活費も考慮して、総合的な費用計画を立てましょう。
日本の大学の学費の平均額
(※各種費用を含む入学1年目の学費合計額)
| 国公立 | 公立(地域内) | 公立(地域外) | 私立 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 28万2000円 | 22万1399円 | 38万2423円 | 25万8434円 | 授業料 | 53万5800円 | 53万6471円 | 53万6391円 | 98万5236円 | 初年度納入金 | 81万7800円 | 83万9988円 | 100万6239円 | 165万3535円 |
出典:旺文社教育情報センター 『2024年度大学の学費平均額』
https://eic.obunsha.co.jp/file/educational_info/2024/0806.pdf
日本への留学生の奨学金制度は?
日本の大学や政府機関、民間団体などが留学生向けの奨学金制度を提供しています。
日本学生支援機構(JASSO)や日本政府の文部科学省の奨学金が代表的ですが、各大学に独自の奨学金が用意されている場合もあります。応募条件や支給額、募集時期は各制度によって異なるため、早めに情報収集を行うことが重要です。
外国人向けの奨学金には、日本に来る前に申し込むものと、来た後に申し込むものがあります。いずれも、日本学生支援機構のウェブサイトなどから検索が可能です。ちなみに日本では返済の必要な「貸与型」奨学金も多いため、きちんと確認しておきましょう。
日本の大学を卒業後の進路について
日本の大学を卒業後、日本国内や海外での就職・進学など多様な進路が考えられます。2022年度中(2022年4月1日から2023年3月31日まで)に卒業した外国人留学生の進路状況について調査した資料では、留学生のうち半数近くの学部卒業生が日本国内での就職という道を選択しています。また、日本国内の大学院などへの進学を選んだ卒業生も2割近くいます。
留学生の卒業後の進路(学部生)・日本国内に留まる場合
| 就職 | 進学 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|
| 44.3% | 19.9% | 12.2% | 76.4% |
出典:独立行政法人 日本学生支援機構
『2022(令和4)年度 外国人留学生進路状況調査結果』
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2024/05/data2022s.pdf
留学生の卒業後の進路(学部生)・出身国に帰る場合
| 就職 | 進学 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|
| 7.3% | 0.5% | 13.8% | 21.5% |
出典:独立行政法人 日本学生支援機構
『2022(令和4)年度 外国人留学生進路状況調査結果』
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2024/05/data2022s.pdf
日本の大学での留学生のサポートや海外から学位を修得できるプログラム
海外からの学生を積極的に受け入れている二つの大学の広報や入試担当者に、それぞれのプログラムの特徴を聞きました。
国際基督教大学(ICU)

回答者:国際基督教大学(ICU)・パブリックリレーションズ・オフィス
- バイリンガル教育の徹底:日英両語を運用可能とする語学プログラム。
- 留学生を区別しない一体型教育:“留学生専用”が不要な共に学ぶ体制。
- 大学院進学率の高さ:国内外含め、大学院進学率は20%超。
JLPを語学要件として履修することになった場合、日本語運用能力に応じたクラスに配置されますので心配はいりません。まず、カリキュラムからきめ細やかに対応しています。例えば、日本語を第一言語とする帰国生などの場合は、“Special Japanese Track”という上級者用の日本語コースがあり、自分の日本語力に合ったクラスを履修できます。留学生の場合も、日本語力に応じた七つのレベル別のクラスに分かれています。
叡啓大学

回答者:叡啓大学・教学課国際担当 上田健治さん
- 課題解決型の学び:SDGsを軸にリベラルアーツと実践教育を融合。
- 留学生の多様性と支援:全授業が日英両語、生活・就職支援が充実。
- グローバルなキャリア形成:メンター制度や企業連携で就職支援。
特に課題解決演習では、本学と提携している企業やNPO、国際機関、地方公共団体などから提示される課題をテーマとして設定し、解決へのプロセスを実践的に学ぶことができます。
開学して4年目の新しい大学で、今年の3月に初めての卒業生がでますが、卒業後も日本で就職する予定です。


※このページは「ライトハウス2025年4月号」掲載の情報を基に作成しています。最新の情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。